目減りが怖い・・・長期の時間分散でリスクをコントロール!
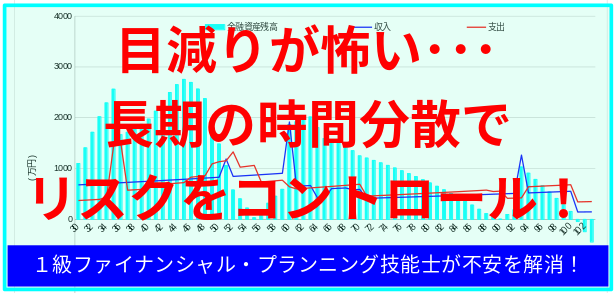
「今度こそ投資を始めよう!」と思い立ったものの、「やはり目減りが怖い・・・。」「ローリスク、ハイリターンなものは無いのだろうか?」「いやいや、そんなに都合が良いものがあるなら、誰もが飛びついているはずだよなぁ・・・。」「こんなに相場の上下が激しくて、いつ始めたら良いのか・・・。」などと悶々とし続けていないでしょうか?
価格が変動するものを売買するなら、損する可能性はつきものだと頭ではわかっていても、精神的には受け入れがたいですよね。それでも得することを期待し、一歩を踏み出すにはどのように考えればよいのでしょうか?
・リスクをコントロールする考え方。
・いつ始めるべきか迷っている方へのヒント。
具体的には次の方法をご紹介します。
- 長期の時間分散投資
価格が変動するものを一括で高値づかみしてしまわないように、買うタイミングを分散させます。高値で買ってしまうときもあれば、安値で買えるときもあり、最終的な損得の振れ幅(リスク)を軽減することができます。
さらに、一定額を定期的に買い続けるドルコスト平均法を採用すれば、高値のときには買う数量を少なくし、低値のときには多数買うという調節を自動的にすることができます。 - 将来の金融資産残高の推移のシミュレーション。
どのような投資をいつ始めると、家計にどう影響するのかを確認することができます。
この記事では想定シナリオにこれらの方法を適用し、長期の時間分散投資の効果と家計への影響を確認していきます。
統計
どんな人たちが長期投資を選択しているのでしょうか?
金融庁のNISA口座の利用状況調査(2022年9月末時点)のデータを元に作成した次の表によると、一般NISAの口座数・貸付額は50歳代が最も多いのに対して、つみたてNISAの口座数・貸付額は30歳代が最も多いことが分かります。
| 年齢階級 | 一般NISA | つみたてNISA | ||
| 口座数 (万口座) | 買付額(億円) (2022年利用枠) | 口座数 (万口座) | 買付額(億円) (2022年利用枠) | |
| 20歳代 | 40 | 882 | 135 | 1690 |
| 30歳代 | 106 | 2852 | 196 | 2859 |
| 40歳代 | 159 | 4123 | 169 | 2328 |
| 50歳代 | 193 | 4985 | 116 | 1501 |
| 60歳代 | 224 | 5757 | 50 | 618 |
| 70歳代 | 227 | 4747 | 16 | 172 |
| 80歳代 以上 | 120 | 1431 | 3 | 17 |
| 出典:「NISA口座の利用状況調査(2022年9月末時点)」(金融庁)のデータを加工して作成 | ||||
現役の給料がまだまだ続く30代の人たちが、あえてつみたてNISAを選んでいる傾向がありますね。若くても資産形成の意識が高い人は、すぐには使わない将来のためのお金を、時間をかけて作ろうとしているのではないでしょうか。
シミュレーション
次のシナリオで、一括投資または長期投資をした場合についてシミュレーションし、効果と家計への影響を比較してみます。
シナリオの設定条件
- 家族条件
| 家族条件 | 歳(現在) | 生計から外れる |
| 夫 | 30 | 100歳で死亡 |
| 妻 | 27 | 100歳で死亡 |
| 第1子 | 0 | 23歳で独立 |
| 第2子 | 3年後に誕生 | 23歳で独立 |
- 投資条件
投資対象の価格は、結果として以下のような変動をしたものとします。(投資時点で将来の価格が決まっているわけではなく、予測に基づいて判断するものとします。)

- その他の詳細条件はこちらを参照。
1. 一括投資で損切り
ではまず、夫35歳時点で思い切って1,000万円を投資した場合はどうなるでしょうか?

30代前半では上昇局面だったので期待していたのですが、価格は50代で随分と下落してしまいました。このままゼロになってしまうのではないかという強い恐怖感に襲われ、51歳で換金(損切り)してしまったとすると、1,000万円→351万円 の目減りとなります。
| 投資条件 | 年齢 | 万円 |
| 一括投資額 | 夫35歳 | 1,000 |
| 一括売却額 | 夫51歳 | 351 |
| 売却額 / 投資総額 = 351 / 1,000 = 0.351倍 | ||
この場合、金融資産残高は次のように遷移します。

教育費のピークと損切りが重なり、大きな痛手ですね。
また、老後資金も限られてしまいそうです。
| 結果 | 年齢 | 万円 |
| 金融資産残高 | 夫70歳 | 1250 |
| 年間生活費 | 夫70-90歳 | 223 |
2. 下落局面から長期投資
では次に、長期的に時間分散して投資をした場合にはどうなるでしょうか?このケースでは、思い立った35歳時点では下落局面を迎えるところでしたが、すぐに積み立てを開始したものとします。

| 投資条件 | 年齢 | 万円 |
| 長期分散投資額 (30万/年ずつ) | 夫35-69歳 | 総額 1,050 |
| 一括売却額 | 夫70歳 | 2,417 |
| 売却額 / 投資総額 = 2,417 / 1,050 = 2.302倍 | ||
このケースでは投資総額に対して大きなリターンを得ることができますね。
もちろん50代の下落局面でつらい時期もありますが、ケース1の一括投資に比べると、その時点の投資総額は限られ、精神的なダメージはまだマシでしょう。また、下落した状況でも買い続けることから、安物大バーゲンのチャンスだと前向きな捉え方もあります。もしくは、放ったらかしで自動積み立てを継続していることから、そもそも運用状況を意識していないかもしれません。
いずれにしてもこのケースでは、ドルコスト平均法が奏功したのと、老後の好機を捉えて換金できたのとで、金融資産残高は次のように遷移します。

老後資金の面でも、ケース1よりゆとりを持てそうですね。
| 結果 | 年齢 | 万円 |
| 金融資産残高 | 夫70歳 | 3,266 |
| 年間生活費 | 夫70-90歳 | 259 |
3. 上昇局面から長期投資
長期の時間分散投資のメリットはわかっていても、目減りするのを目にしたくない。という思いから、30代後半は様子を見て、40代前半で価格上昇し始めたときに積み立てを始めた場合、どうなるでしょうか?

| 投資条件 | 年齢 | 万円 |
| 長期分散投資 (36万/年ずつ) | 夫42-69歳 | 総額 1,002 |
| 一括売却 | 夫70歳 | 2,313 |
| 売却額 / 投資総額 = 2,313 / 1,002 = 2.308倍 | ||
おや?と思いましたか?上昇局面を狙って積み立てを開始したはずなのに、運用成果がケース2と大して変わりませんね。
そうです。ケース2では30代後半の下落局面では安物大バーゲンで購入できたこともいく分か寄与していたのです。「いつが始めどきなのだろう・・・。」と迷っても、今回の例では運用成果に大した違いは出ませんでしたね。

このケースもケース1に比べてゆとりのある老後を過ごせそうです。
| 結果 | 年齢 | 万円 |
| 金融資産残高 | 夫70歳 | 3,210 |
| 年間生活費 | 夫70-90歳 | 259 |
まとめ
価格が変動するものを売買するなら、損する可能性はつきものだと頭ではわかっていても、精神的には受け入れがたいですよね。今回ご紹介した長期の時間分散投資でも、もちろん損する可能性がなくなるわけではありませんが、高値で買ってしまうときもあれば、安値で買えるときもあり、最終的な損得の振れ幅を軽減することができます。一度始めたら短期的な価格変動に一喜一憂せず、じっくり時間をかけて向き合ってみてはいかがでしょうか?また、すぐに使わないお金であれば、換金のタイミングも好機を狙ってある程度コントロールできますね。
とはいえ、個人の価値観や諸事情により、どうしても投資が怖い、小さくても目減りは嫌だ、そもそも投資の余力がない、などのケースもあります。その場合も、一生安心の家計を維持するには、対策を考えておくことをお勧めします。生活費、教育費、働き方、投資、保険、節税など、様々な面での見直し方法がありますので、総合的に見直すと良いでしょう。
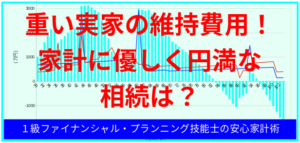
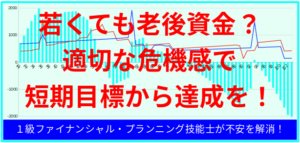
“目減りが怖い・・・長期の時間分散でリスクをコントロール!” に対して1件のコメントがあります。