老後の収入減に要注意!家計の計画的なダウンサイジングを!
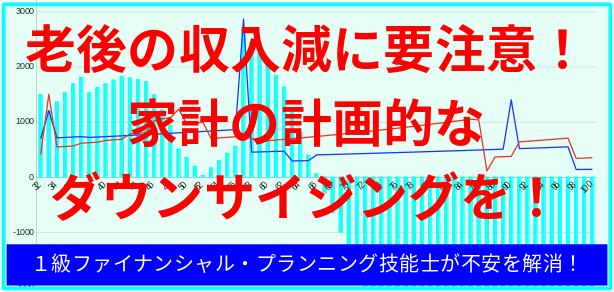
50代で子どもも独立し、住宅ローンも完済した。ようやく肩の荷が下り、さらに退職金というご褒美まで入ってきて、これからは自分のために時間もお金も使おうと、ゆとりのある生活を謳歌したいと思うことでしょう。一方、再雇用や再就職しても収入は半減、もしくは年金が主な収入となるかもしれませんが、本当にゆとりがあるのでしょうか?
現役中と同じような感覚で支出を続け、あれだけあった退職金や貯金を取り崩していき、気づいたら底をつきてしまった・・・という状況は避けたいですよね。
・現役並みの支出を続けたときの将来家計への影響
・老後生活のダウンサイジングの重要性
・考え方 (イベント契機 or 徐々に)
具体的には次の方法で分かります。
- 将来の金融資産残高をシミュレーション
- 金融資産残高をプラスに維持できるように老後の生活費を調整
これまで続けてきた生活費を削減するのは精神的にもストレスになりますが、自分なりに受け入れやすい考え方をしてみましょう。例えば次の考え方があります。
- 子どもの独立、退職などのイベントを契機として生活費を減らす。
子どもが独立後、徐々に生活費を減らしていく。
世代ごとの消費支出は?
総務省統計局の家計調査(家計収支編)の2021年のデータをもとに作成した以下の表によると、確かに世代ごとの消費支出は50代→60代→70代以降と減って行く傾向があります。
| 年齢 | 毎月(円) | 毎年(万円) |
| 夫30歳-39歳 | 233,078 | 280 |
| 夫40歳-49歳 | 287,801 | 345 |
| 夫50歳-59歳 | 287,933 | 346 |
| 夫60歳-69歳 | 251,343 | 302 |
| 夫70歳- | 190,815 | 229 |
| 出典:「家計調査(家計収支編)」(総務省統計局)の2021年のデータを加工して作成 | ||
年齢とともに活動量が減るので、無意識でダウンサイジングできている部分もあるかもしれませんが、何となくで済むとは限りません。個人の状況に応じて計算し、計画的にダウンサイジングすることで、一生安心して家計をやりくりできるといいですね。それでは、その計算の例を見てみましょう。
シミュレーション
〜老後の生活レベルとダウンサイジングの効果は?〜
次の例では、ダウンサイジングしなかった場合に対して、2通りの考え方で対処してみます。
シナリオの設定条件
| 家族条件 | 歳(現在) | 生計から外れる |
| 夫 | 35 | 100歳で死亡 |
| 妻 | 32 | 100歳で死亡 |
| 第1子 | 5 | 23歳で独立 |
| 第2子 | 2 | 23歳で独立 |
| 収入条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) |
| 給与 | 700 | 夫35-60歳 | 1 |
| 350 | 夫61-65歳 | 1 | |
| 退職金 | 2000 | 夫60歳 | 0 |
| 年金 | 216 | 夫65歳-終身 | 1 |
| 72 | 妻65歳-終身 | 1 |
(夫35歳時点の物価水準で表示)
その他の詳細データはこちらを参照。
1. 現役並みの支出を継続
ではまず、現役並みの支出を継続した場合はどうなるでしょうか?ここでは、子どもが独立したにもかかわらず、生活費を下げずに80代まで過ごした場合を考えてシミュレーションしてみます。(90代は別途計上する介護費用のウェイトが大きくなると想定し、生活費は下げますが、ここでは割愛します。)
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) |
| 生活費 | 300 | 夫35歳-39歳 | 2 |
| 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | |
| 352 | 夫50歳-55歳 | 2 | |
| 352 | 夫56歳-69歳 | 2 | |
| 352 | 夫70歳-89歳 | 2 |
すると、結果は次のようになります。

収入が減ったにもかかわらず現役並みの支出を続けていては、到底生活は成り立ちませんね。
2. イベント契機でダウンサイジング
では次に、イベントを契機として生活費を下げてみてはいかがでしょうか?ここでは、子どもが独立する56歳、定年退職する60歳を契機として、生活費を次のように下げてみます。これらのイベントが生活費を下げる理由づけになり、受け入れやすいのではないでしょうか?
| 支出条件 | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) |
| 生活費 | 300 | 夫35歳-39歳 | 2 |
| 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | |
| 352 | 夫50歳-55歳 | 2 | |
| 250 | 夫56歳-60歳 | 2 | |
| 220 | 夫61歳-89歳 | 2 |
(夫35歳時点の物価水準で表示)
このようなダウンサイズの結果、金融資産残高は次のようになります。

イベント契機で計画的にダウンサイジングした結果、金融資産は何とかプラスに維持できそうです。
しかし、イベント契機であっても、現役時代の感覚が抜けず、急な生活費ダウンを受け入れられないおそれもあります。また、目立ったイベントがない60代〜80代の間、生活レベルを一定に維持してしまうと、60代の初めは急な生活費ダウンで生活が苦しく感じ、一方、活動量が減った80代の後半では過剰になるなど、実態の変化に適していない可能性があります。
イベント契機だけでなく、定期的に計画を見直していくことが必要ですね。
3. 徐々にダウンサイジング
では、子どもが独立後に徐々にダウンサイジングを進める場合はどうでしょうか?ここでは物価上昇率がずっと2%と想定し、子どもが独立した56歳以降で、生活費を変動率-0.5%で徐々にダウンさせてみます。
| 55歳まで | 万円/年 | 年齢 | 変動率(%) |
| 生活費 | 300 | 夫35歳-39歳 | 2 |
| 336 | 夫40歳-49歳 | 2 | |
| 352 | 夫50歳-55歳 | 2 |
(夫35歳時点の物価水準で表示)
子どもが独立する56歳以降は、額面で-0.5%ずつ減らしていきましょう。つまり、物価が上昇する一方で、生活費の額面も減らしますので、生活費の実質的な価値はもっと下げていることになります。
| 歳(55歳以降)→ | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ・・・ | 65 | ・・・ | 70 | ・・・ | 80 | ・・・ | 90 |
| 額面(万円)※1→ | 523 | 520 | 518 | 515 | 513 | 510 | ・・・ | 497 | ・・・ | 485 | ・・・ | 461 | ・・・ | 439 |
| 実質価値(万円)※2→ | 523 | 510 | 498 | 485 | 474 | 462 | ・・・ | 408 | ・・・ | 360 | ・・・ | 281 | ・・・ | 219 |
| ※1:生活費(額面)の変動率:-0.5%で減少するものとする。 ※2:物価上昇率:2%で割戻し、55歳時点の現在価値で表現なお、物価上昇率2%が継続すると、夫35歳時点で年間352万円と同等の生活費は、55歳時点で523万円の額面になるため、本表では523万円でスタート。 | ||||||||||||||
このように徐々にダウンサイジングしていくと、金融資産残高は次のようになります。

この場合、実質的には生活レベルを徐々に落としていっていることになりますが、急な生活費の削減は生じないまま、生涯を通して金融資産残高を維持することができますね。
ただしこの場合、毎年の生活費の変化が少ないので、ともすれば昨年と同じ生活レベルを維持してしまう恐れがあります。毎年着実にダウンサイジングできるように、予算に明確な数値を決め(例えば、昨年に比べ、今年は毎月の生活費を1万円減らすなど)、守り続けることが重要になりますね。
まとめ
子どもの独立や住宅ローンの完済など、肩の荷が下り、計画的にゆとりのある生活を楽しめるのは素晴らしいことだと思います。しかし、いつまでも現役中と同じような感覚でゆとりがあると思ってはいけませんね。後になって慌てないように、ぜひ計画的にダウンサイジングをすることをお勧めします。その際、本記事でご紹介した2通りの方法(イベント契機 or 徐々に)も参考に、自分の受け入れやすい考え方をしてみてはいかがでしょうか?
個人の価値観や諸事情に合わせて、なるべくストレスの少ない方法でダウンサイジングできるといいですね。生活費、教育費、働き方、投資、保険、節税など、様々な面での見直し方法がありますので、総合的に見直すと良いでしょう。
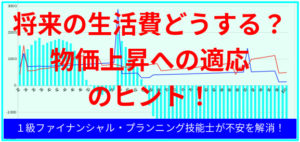
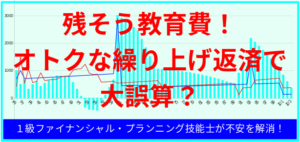
“老後の収入減に要注意!家計の計画的なダウンサイジングを!” に対して1件のコメントがあります。