マイホームは一生モノ?リセールバリューへの過度な期待は禁物!
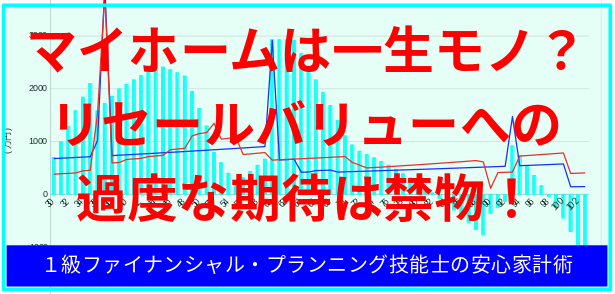
大ショック!ようやくの思いで買ったマイホームがイマイチだった・・・。日々のハードな仕事にも耐えて手に入れた汗と涙の結晶なのに・・・。
多くの人にとって人生最大の買い物でこんなことになったら、ショックは大きすぎますよね。「時間を戻せるものなら戻したい。」「もう一度チャンスがあれば買い直したい。」そんな気持ちになるでしょう。
買ったばかりの家ならリセールバリューに期待して、同じ価格帯の家を買い直せると思いたいところですが、そんなにうまくいくのでしょうか?これから子育てや教育費など大きなお金が必要になるときに、期待する値段で売れなかったら困りますよね。
では、いつなら買い替えられるのでしょうか?はたまた願いは叶わないのでしょうか・・・?
・マイホーム売却による
将来家計への影響
・リセールバリューと
自分にとっての価値
具体的には売却をするかどうかや、売却時期の条件を変えて、将来の金融資産残高の推移をシミュレーションすることでこれらを検証します。
感情的になって買い替えを進めて、後でもっと後悔することのないように、将来の家計を見通して慎重に判断しましょう。
築後20年で価値がほぼゼロに?
国土交通省の「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」の「中古戸建住宅の価格査定の例」によると、ポイントは次のとおりです。
・住宅の市場価値は、経年により減少。
・戸建住宅の場合、築後20年で価格はほぼゼロに。
(出典:「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」の「中古戸建住宅の価格査定の例」(国土交通省、https://www.mlit.go.jp/common/000135252.pdf、2023年3月18日アクセス))
「築後20年で価格がほぼゼロに」と聞いて、皆さんはどう考えますか?
- 価格がゼロにならないうちに早く売却してしまわなければ!
- 20年間住めばしっかりモトが取れるならば、20年後に売却しよう!
- 自分にとっての真の価値は?
さて、どれが妥当な反応なのでしょうか?次のシナリオでシミュレーションしてみましょう。
シミュレーション
シナリオの設定条件
- 家族条件
| 家族条件 | 歳(現在) | 生計から外れる |
| 夫 | 30 | 100歳で死亡 |
| 妻 | 27 | 100歳で死亡 |
| 第1子 | 0 | 23歳で独立 |
| 第2子 | (3年後に誕生) | 23歳で独立 |
- その他の詳細データはこちらを参照。
1. 築後すぐに買い替え
「新築とほぼ変わらないので、リセールバリューに期待!」「価格が下がる前に早く売ろう!」とする場合、どうなるでしょうか?このケースでは、36歳で新築の家を買ったばかりなのに、37歳ですぐ次の家に買い替えた場合について、次の条件のもとでシミュレーションしてみます。
| ケース1. 築後すぐに買い替え | 万円 | 年齢 | ||
| 第1の家 | 購入にかかる費用 | 3,800 | 夫36歳 | |
| 原資 | 頭金(預金取り崩し) | 1,000 | ||
| 親の援助 | 300 | |||
| 住宅ローン借入 | 2,500 | |||
| 売却による収入 | 3,200 | 夫37歳 | ||
| 住宅ローン返済残高 | 2,430 | |||
| 住宅ローン完済後の残金 | 770 | |||
| 第2の家 | 購入にかかる費用 | 3,800 | 夫37歳 | |
| 原資 | 第1の家完済後の残金 | 770 | ||
| 住宅ローン借入 | 3,030 | |||
| 売却による収入 | 936 | 夫93歳 | ||
※各年齢での物価水準で表示
※購入にかかる費用、売却による収入は諸費用折込後
元々3,800万円かけて購入した第1の家は、売却により3,200万円しか戻らなかったものとします。(「ほぼ新築なのになぜこんなに下がるの?」と思うかもしれませんが、いくら築浅と言っても、一度でも住んだことのある家は「新築」とは言えず、誰の手垢もついていない新築ならではの価値(いわゆる新築プレミアム)の喪失があります。また、購入時・売却時の諸費用もそれぞれありますので、物件の価格だけでは済まないのです。)
第2の家を購入時に、第1の家売却後の残金(770万円)だけでは足りない3,030万円を、住宅ローン借入で工面しました。もともと37歳時点で残っていた第1の家の住宅ローン残高(2,430万円)より600万円ほど借金を増やしたことになります。
600万円は冷静に慣れば、通常のサラリーマンが何年もかかって返すほどの大金です。(しかも、金利分が上乗せされます。)しかし、既に2,430万円の住宅ローン残高を抱えていた状況をベースに考えてしまうと、感覚が鈍ってしまうかもしれませんね。
この判断の結果、このケースでは金融資産残高は次のように推移します。

住宅ローンの返済が72歳まで続き、老後資金がショートしてしまいます。第2の家のために、増やした住宅ローン負債は、たかが600万円と思いきや、されど600万円(+金利)であり、家計への影響は大きかったのです。
2. 築後25年で買い替え
では、次のように考えて築後25年(夫61歳)で買い替えることにしてみます。
- 築後20年以上経っているので家の価格はほぼゼロ。もう十分モトは取れた。
- 土地の分の価格は残っているので、売却による収入681万円を次の家の購入の足しにできる。
- 現役を引退、子どもも巣立ち、通勤や教育の都合にとらわれず、夫婦で十分なサイズの中古の家(購入にかかる費用は1,681万円程度)に住めれば十分。賃貸で毎年100万円で20年間生活するより断然安い。
- 退職金も入り、住宅ローンを1,258万円借り入れる余裕もある。
さて、これは合理的な判断でしょうか?次の条件でシミュレーションしてみます。
| ケース2. 築後25年で買い替え | 万円 | 年齢 | ||
| 第1の家 | 購入にかかる費用 | 3,800 | 夫36歳 | |
| 原資 | 頭金(預金取り崩し) | 1,000 | ||
| 親の援助 | 300 | |||
| 住宅ローン借入 | 2,500 | |||
| 売却による収入 | 681 | 夫61歳 | ||
| 住宅ローン完済後の残金 | 423 | 夫61歳 | ||
| 第2の家 | 購入にかかる費用 | 1,681 | 夫61歳 | |
| 原資 | 第1の家完済後の残金 | 423 | ||
| 住宅ローン借入 | 1,258 | |||
| 売却による収入 | 936 | 夫93歳 | ||
※各年齢での物価水準で表示
※購入にかかる費用、売却による収入は諸費用折込後
実際に金融資産残高のシミュレーションをしてみると、次のようになります。

価格ゼロの家を売るのだから損はないだろうと思いきや、今回も老後の資金がショートしてしまいました。せっかくの退職金で一時的に資産残高が回復したものの、住宅ローンを抱えている老後の状況では急ピッチで減ってしまい、家計の維持が難しそうですね。
3. 買い替えなし
では、不本意ながら初めに買った家に住み続け、買い換えない場合について、シミュレーションしてみます。
| ケース3. 買い替えなし | 万円 | 年齢 | ||
| 1度のみ購入・売却 | 購入にかかる費用 | 3,800 | 夫36歳 | |
| 原資 | 頭金(預金取り崩し) | 1,000 | ||
| 親の援助 | 300 | |||
| 住宅ローン借入 | 2,500 | |||
| 売却による収入 | 936 | 夫93歳 | ||
| ※それぞれ購入時の物価水準で表示 ※購入にかかる費用、売却による収入は諸費用折込後 | ||||
するとどうなるでしょうか?
なお、夫93歳で介護費用を捻出するためマイホームを売却するものとします。(介護施設に移った後はマイホームは不要。)

今度は家計の面では一生安心して生活できそうですね。「築後20年でほぼ価格ゼロ」とはいえ、自分にとっては十分に価値があるものだったのです。マイホーム購入は、生涯に渡る住居費用を一括で前払いしたようなものだったのですね。
今回のシナリオでは結局、家計の面からは住み替えないのが合理的だという結果になりました。このことは、いかに第1の家を購入するときの判断が重要だったかを示しています。
まとめ
多くの人にとってマイホームの購入は初めてのことであり、失敗することもあるでしょう。しかし、「今回は残念だったけど、一度転んだところでまたやり直せばいいさ。今度こそ後悔のない家を買い直そう!」という判断は本当に大丈夫でしょうか?今回シミュレーションしたシナリオのように、将来の家計に大きな打撃を与えてしまう可能性もありますので、十分に吟味したいですね。
何とか家の買い替えを正当化したい気持ちにもなると思いますが、今回のシミュレーションで確認した次のポイントを踏まえて慎重に判断することをお勧めします。
- 買った直後にすぐ買い替えても、諸費用や新築プレミアムの喪失分も加味すると、住宅ローン負債等を増やさない限り、前と同じ価格帯の家を購入できるわけではない。
- 築後20年で価格はほぼゼロになるといっても、それは他人が購入する場合の話。自分が住むからこそ一生モノの価値がある。それを安易に低価格で手放して、次の住居に資金投入するのは、家計の面では大きな損失である。
とはいえ、個人の価値観や諸事情により、どうしても家の買い替えを優先せざるを得ないケースもあります。その場合、買い替えた後に後悔しないように厳しく見積もり、対策を考えておくことをお勧めします。生活費、教育費、働き方、投資、保険、節税など、様々な面での見直し方法がありますので、総合的に見直すと良いでしょう。
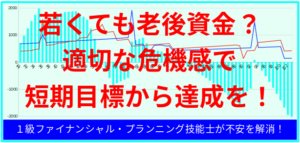
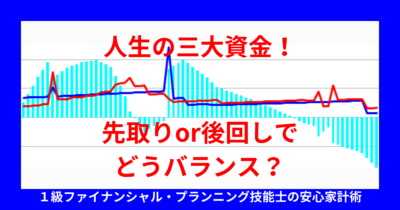
“マイホームは一生モノ?リセールバリューへの過度な期待は禁物!” に対して1件のコメントがあります。