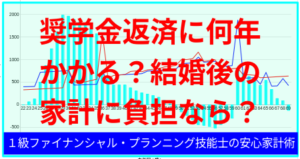住宅ローンは頭金が多いとオトク!手元の貯金をいくら残す?
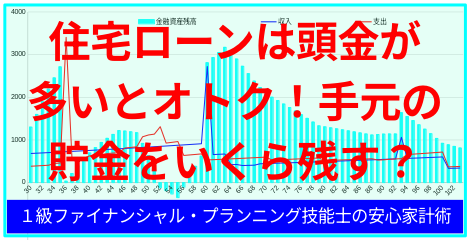
「うっそぉー!金利だけで◯百万円も?こんなお金があったら他のことに使いたいよー。」
普段の買い物とは桁違いの◯千万円ものマイホーム。その金利だけでもこんな額になるとはビックリですよね。
「ならば、頭金を払えるだけ払って金利の負担を減らそう!早く完済すれば支払い金利が浮いてオトクだし、その分、老後のゆとり費用にも回せるぞ。」と考えるかもしれません。
しかし、「これから子どもが大きくなり、教育費が増えてきても大丈夫だろうか?病気や事故、リストラで収入がガクンと減るなんてことは考えたくないが・・・。」という不安もあるでしょう。ある程度は手元に貯金を残しておいたほうが安心できそうですね。
とはいえ、こんなに大きな金利の負担を覚悟してまで、どれだけ手元に貯金を残す必要があるのでしょうか?
・頭金をたくさん払って金利負担を減らそうと考えている人。
・頭金を払い過ぎて今後の家計が破綻しないか不安な人。
住宅購入で頭金の決め方は?手元に貯金をいくら残す?
金利を支払うのがもったいないと感じ、目一杯頭金を支払いたくなるところですが、頭金はライフプランに基づき将来の家計をシミュレーションして決めることをお勧めします。
逆に、頭金を払えるだけ払ったり、今後◯ヶ月の生活予備費(もしものときの備え)だけを残すのは危険です。
なぜ生活予備費だけでは危険なのか?
教育資金や老後資金など、家計の支出はには波があり、貯蓄を取り崩さなければいけない時期もあるためです。想定外に備えた生活予備費だけではなく、想定内のこれらの波を見越した資金余力が必要になります。
頭金をどれくらい払っている?
皆さんは頭金をどれくらい払っているのでしょうか?「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」(国土交通省) (※)を加工して作成した次の表によると、一戸建てと集合住宅でそれぞれ、約900万円(購入資金の約20%)、1400万円(購入資金の約30%)となっています。
| 一次取得者の購入資金(令和4年度分) | ||
| 一戸建て | 集合住宅 | |
| 自己資金(万円) | 869 | 1,438 |
| 借入金(万円) | 3,205 | 3,610 |
| 購入資金総額(万円) | 4,074 | 5,048 |
| 自己資金比率 | 21.3% | 28.5% |
| 「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」(国土交通省) (※)を加工して作成 ※ https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001610299.pdf | ||
なかなか皆さん、頭金を頑張って支払っているのですね。その後の家計で困らない程度に、手元に貯金を残していればよいのですが・・・。
この記事では、実際にどれだけ頭金を支払うと、その後の家計にどのような影響があるのか、次のシナリオの設定条件でシミュレーションしてみます。
シミュレーション
〜住宅購入で貯金をいくら残す?頭金の額により家計は?〜
シナリオの設定条件
- 家族条件
| 家族条件 | 歳(現在) | 生計から外れる |
| 夫 | 30 | 100歳で死亡 |
| 妻 | 27 | 100歳で死亡 |
| 第1子 | 0 | 23歳で独立 |
| 第2子 | 3年後に誕生 | 23歳で独立 |
- 住宅費用条件
次の3つのケースで比較してみます。
| 比較項目 | ケース1 | ケース2 | ケース3 |
| 購入費用(万円) | 4100 | ||
| 頭金(万円) | 2900 | 2500 | 800 |
| 購入時(夫36歳時点)に手元に残す貯金(万円) | 33 | 415 | 2061 |
| 借入額(万円) | 1200 | 1600 | 3300 |
| 毎月返済額(万円) | 7.0 | 8.5 | 13.0 |
| 金利支払総額(万円) | 271 | 339 | 1033 |
| 完済年齢 | 52歳 | 54歳 | 63歳 |
- その他の詳細データはこちらを参照
1. 目一杯の頭金で貯金ゼロに
ではまず、住宅を購入する夫36歳時点で、目一杯の頭金をドーンと払い、その時点の手元の貯金がほぼゼロになるケースについてシミュレーションしてみます。その代わり月々の返済額は7万円まで抑えられることから、貯金はまたすぐ貯まるだろうと楽観的に考えたのです。この場合、将来の家計はどうなるでしょうか?

夫36歳でマイホーム購入により貯金をほぼゼロにした後、しばらくは目論見どおり貯金が回復してきました。しかしその後、教育費が急増した40代後半で急に減りだし、ピークの夫50代で資金ショートしてしまいました。
金利の負担を減らせた分、老後資金はかなり余裕となりますが、それ以前に現役時代に破綻してしまっては、元も子もありません。また、安定した収入を維持できるとも限らないこのご時世で、貯金をゼロにまであえて減らすというのはリスクが伴いますね。
2. 約1年分の予備費を残せば安心?
では次に、住宅を購入した夫36歳時点で、約1年分の生活予備費として400万円程度の貯金を手元に残したケースについて、シミュレーションしてみます。解雇や倒産、急病などで、もし急に収入が途絶えたとしても、1年間は生活できる余力があれば十分と考えたのです。この場合、将来の家計はどうなるのでしょうか?

なんと、この場合も夫50代で資金ショートしてしまいました。直近の1年分の生活は何とか乗り越えれたとしても、長期的な見通しがなければやはり危険ですね。
3. ライフプランに基づく頭金なら?
では最後に、ライフプランに基づき、教育費のピークに耐えられるように、頭金を調整してみましょう。この場合、頭金を800万円まで抑えます。住宅を購入する夫36歳時点で、頭金を支払ってもまだ2000万円以上も手元に貯金を残すのです。この時点ではもっと頭金に回さないと金利の支払いがもったいないと感じるかもしれませんね。実際に金利支払総額は1000万円程度と、他のケースに比べて700万円前後も多く支払うことになります。

しかし、その後の家計は教育費のピークの夫50代でギリギリとなり、これ以上頭金を無理してはいけないと気づきますね。
まとめ
頭金をどれだけ支払い、手元に貯金をいくら残せばよいのかは、ライフプランに基づき将来の家計をシミュレーションして決めることをお勧めします。
「一律に生活費◯ヶ月分」と言ってもらったほうが分かりやすいと思うかもしれませんが、長期的には支出に大きな波があります。教育費や老後資金など、貯蓄を取り崩さなければいけない時期も含めて家計を維持できるか、試算しなければ分かりません。
金利の支払いをもったいないと感じるかもしれませんが、長期で付き合っていく住宅ローンですから、ぜひ長い目で将来の家計を見通しを立てて、頭金の金額を決めましょう。
とはいえ、個人の価値観や諸事情により、どうしても手元に貯金をあまり残せないケースもあります。その場合、教育費のピークの時期や老後になってから慌てないように厳しく見積もり、対策を考えておくことをお勧めします。生活費、教育費、働き方、投資、保険、節税など、様々な面での見直し方法がありますので、総合的に見直すと良いでしょう。